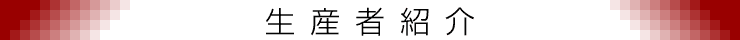
生産者紹介
匠の箱
- 表の見方
 所在地
所在地 名前
名前 店舗名
店舗名 職業
職業 おすすめ商品
おすすめ商品 生年月日
生年月日 星座
星座 座右の銘
座右の銘
 山形県
山形県 高木正二さん
高木正二さん 匠の箱
匠の箱 ぶどう蔓工芸職人
ぶどう蔓工芸職人 角丸丸底ライン2
角丸丸底ライン2 1951/04/04
1951/04/04 おひつじ座
おひつじ座
私のこだわり
高木さんの山ぶどうつる かごバッグの魅力ってなんですか?国産の山ぶどうつるの素材のすごさ、そしてそれを採集から行っていることですね。
外国産の山ぶどうは紙にたとえられ、国産の山ぶどうはゴムにたとえられるほど、国産の山ぶどうつるは丈夫なので、かなりの力で引っ張ってもつるが切れたりすることがほとんどないんですね。山ぶどうつる1本で、車1台をひっぱることができますから(笑)。
また、東北の厳しい風雪に耐え抜いているので、水にも、乾燥にも強く、雨に濡れても乾かすだけで元に戻ります。
そして、使えば使うほど艶が出て柔かくなり、使う人に馴染みます。
小さなお孫さんに、うちのかごバッグを大きくなったら使わせて、とせがまれているお客さんもいるのですが、そのお孫さんが、おばあさんになるまで、ますます味わいを増しながら、楽しむことが出来るのが、山ぶどうつるです。 その子の子供も、まだまだ使えます(笑)。
そんな山ぶどうつるですが、採集するのは本当に大変です。
時には断崖絶壁を行くこともあり、落石、転落、遭難などの命の危険にさらされながら行うこともある、命がけの作業になります。遭難しかけたこともあるし、この間も、仲間を助けようとして、自分が滑落しそうになりました(笑)。

メッセージはありますか?
山ぶどうつるは、元来、日本人にとって、みそと同じくらいの生活必需品だったんですね。
100年以上前に作られた、当時山菜取りに使われた山ぶどうつるのかごバッグが工房にあるのですが、使った人の背中の丸みに合わせ、ますますしなやかに、 ますます味わい深くなっているんです。
使えば使うほど、ますます味わいを増しながら楽しむことが出来る一生もの、それが、山ぶどうつるです。
採集するところから、一つ一つ丁寧に編みあげる かごバッグの、本物の素材のすごみを楽しんでもらえれば嬉しいですね。

生産者の横顔
お客さんが自慢に来てくれる!かごバッグ高木さんのお客さんの中には、自分のかごバッグがこんなに味わい深くなったと、見せに来てくれることがあるそうです。
「いい色になったねえ!とお客さんと一緒に喜ぶんですよ」と言う高木さんは、茶目っ気たっぷりの暖かい笑顔を浮かべていますが、ひとたび山に採集に入ると、別人のように厳しい棟梁の顔になります。
高木さんは険しい山の中で山ぶどうつるを見つけると、嬉しそうに「うまそうな木だ!」と全員に声をかけます。
そして、全員で声をかけあって互いの位置を確認しながら、手際よく高い木に登り、力を合わせて、山ぶどうつるを採集していきます。採集されたつるは、その場で皮をはがさなければなりません。立っているのも大変な急な斜面で、つるを取るのも、皮をはがすのも、困難な作業です。
そして、背中いっぱいに、大切な山ぶどうつるを背負って、並んで山をおりてきます。
高木さんは、「これで作るかごバッグは、自分の娘だよ」といって、顔をくしゃくしゃにして笑いました。
東北の厳しい自然に磨かれ、愛されてきた山ぶどうつるのかごバッグには、その希少な素材に命をかける、作り手の魂がこもっています。

奥羽山脈を背にした
吾妻連峰の裾野に広がる米沢盆地にある工房は
四季折々の風景に恵まれた静かな町
山形県米沢市福田町
冬は 一面 真白な世界
全てが雪に埋もれる豪雪地帯
雪の美しさと厳しさを 身を以って味わう
山ぶどうのつるは そんな自然からの贈り物
毎年 六月頃の梅雨時期になると
つる編みの手を止め 吾妻の山奥へ入り
背負子(しょいこ)にいっぱいのつるを担ぎ
また山を降りる
そして 今日も山の神様に感謝をし
黙々と籠を編む
自然との共存共栄を守りながら
年々貴重になるつるを 大切に作品に仕上げる
百年後、私の創った籠が見事に艶を増し
生活の中に存在していることを想像しながら・・・。
高木正二











































